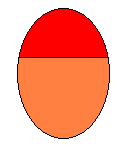 フカセ釣りについて
フカセ釣りについて
(2005年3月3月6日更新)
| 私の愛竿 | gamakatsu がま磯ATTENDER 1号 5.3m がま磯プレシードSP 1号 5.3m がま磯グレ競技SP2 1.75号 5m がま磯チヌ競技SP 1号 5.3m |
現在のメインロッド 旧メインロッド現在主に団子用 宇和海、南紀等への遠征用 サブロッド(kabeさんから無期限借用中) |
| リール | SHIMANO BB-X TECNIUM 3000T DAIWA EMBLEM-Z 2500 LBT |
テクニウムもかなり草臥れていて、 BBX TYPE1の購入検討中 |
| 道糸 | 2号 さほど銘柄にはこだわらない。 主に銀鱗ゼロゼロを使用 |
5〜10回の釣行で交換 |
| ハリス | サンライントルネードVハード シーガーグランドマックスFX |
普段チヌには1.2(1.25号)を主に使用。 遠征時は1.75号まではVハード。それ以上の号柄だとVハードは硬すぎるためFX使用。 |
| 針 | オーナー改良チヌ1〜2号 | 特にフカセユースでお気に入り。ヒネリ無しで針先のネムリもなし。アワセに対して力が分散せず立ちがいい。 その他はがまかつ派。 |
| 浮き フカセ |
フカセ プロ山元浮きを主に使用。 その他釣研Tフロートコルク、 エアゾーンの使用が多い。 |
プロ山元浮き ◎感度、仕掛けや潮への馴染み、また強度(耐久性)抜群。現段階では値段的にもこれがあればいい、という感じ。 主にG2使用。0号Sサイズから3B遠投くらいの範囲で幾つか持っている。G2は複数。 W-18タイプは重心低いらしいので使っていない。 Tフロートコルク ○小型高浮力で使いやすい。主に2B、3Bで使用。 ×強度が最悪。すぐに塗装(特に糸穴部分)がひび割れて水が染み込み浮力が変わる。もう少しなんとかならないものだろうか... エアゾーン ○重量もあり遠投時便利。また初めての場所で様子を探るには非常に便利。樹脂性のわりに強度あり。サイズも小型から大型まである。なんといってもガン玉でなく浮きで浮力調整できるため、非常に微妙な(感覚的)な調整ができる。 ×重心が低すぎて仕掛けへの馴染みが悪すぎる。浅棚では使えない。 |
| 撒き餌杓 | 釣研マック60 がまかつ まきーな競技SP 60cm まきーなSP 50cm |
マックシリーズは非常にいい。プラスチックカップでOK(軽いし安いし)。ちゃんとカップを濡らしながら使えば問題なし。 |
| フローティ ングベスト |
がまかつ 背中に「がま磯」とあるモデル。 マルキュー PAライフジャケット |
マルキューのはMFG紀州釣り大会で抽選でもらったもの。 今のところ主にはがまかつを使用。 |
| ブーツ | がまかつ フェルトスパイクブーツ(GM-395) シマノ クロロプレーン性の冬用モデル |
冬場以外はがまかつのものを使用。 シマノのこのブーツは暖かくて冬場は重宝。しかしソールが固すぎて、接地感とグリップがイマイチ。磯歩きは少し不自由。 |
| 防寒着 | シマノの型落ち。 取り外し式のダウンジャケットインナーが着いている。 |
最新のものに比べるとインナーが分厚いので若干ごわごわ感あり。が、暖かい。 一応吸湿発熱素材だが、ダウンインナーの外側にあるのは効果低いんじゃ... |
| サングラス | TALEX 度付き カラー:トゥルービュースポーツ フレームはZEAL neoAVENGE |
2005年2月購入。念願の一品。 |
| 小物 | ガン玉 G7,G5,G2,B,2B常備 ゴム管 蛍光ゴム管 爪楊枝 サルカン ローリングスイベル8号 シモリ玉 釣研半円シモリ |
シマノの小物入れに入れている。 |
| その他 | そりゃ色々あります。 |
(2005年3月3月6日更新)
| 刺し餌 | オキアミ生 マキエのブロックから取り分ければ充分であるし、その方が食いが いいような気がする。あまりパック餌は買わない。 練り餌 マルキューの食わせ練り餌チヌを中心に使用。マキエの粉と混ぜ合わ せることで、バラケ性を調整できる。単体使用は硬すぎ。 白の方は粘り気が強すぎて使い辛い(べちゃべちゃした感あり)。 その他 岩に張り付いているジンガサ、フナムシなど捕まえて使うことあり。 こんなことをやってるときは大体釣れてない... |
| 撒き餌 | 半日の釣行で、 オキアミ生・・・3〜6kg 冬場は3kgでも多いくらい。 集魚材 チヌパワームギorチヌパワーV9遠投 + オカラダンゴ 高集魚の集魚材がどんどん出てきていますが、どうも使い辛い。 集魚はエサトリも集めます。要はバランス。 チヌの場合は濁り...いや細かな粒子が海中に漂う状況を作ることも 重要なのでオキアミだけでは心許ない。オキアミ+ヌカ+サナギ粉とい った組み合わせでも充分にチヌは釣れるが、杓への付着やバラケとい った操作性はやはり集魚材に分あり。 私は上の3つがあれば充分です。 その他 冬場や春先にアミエビを1〜2kg使用することあり。ただし小アジがい ると悲惨な目にあう... |
| 人間の餌 (釣りのとき) |
私は釣りをしていると、飯を食う時間ももったいないと思うタイプなので、手間 が掛からないものがベストです。 最近は、カロリーメイト(チョコレート味)が主食となっています。 飲み物もあまり飲まないので、脱水にならないように、吸収のよさそうなポカリ スエットの500mlボトルを買っていきます。 大塚の製品ばっかりだなぁ。 |
| ポイント | 私はコスト面と自由度の関係から、車で近くまで行けるような地磯で釣る ことが圧倒的に多いです。 フカセでやる場合は、のっこみ期と厳寒期を除けば、潮流がある程度ある 方が釣り易いと思います。瀬戸内海は干満の差が大きく、潮流の速いポ イントが多いので色々なところで釣りができます。 岬や湾の出入り口付近の磯が理想ですが、結構、こんなところで?と思う ような場所で食ってくることも多いものです。 地磯からのチヌ釣りのポイントは浅場が必然的に多くなります。 が、こと チヌに関しては必ずしも水深は必要無いので、気にすることはありません。 干潮時に1ヒロもあれば十分でしょう。ただし、少し沖に落ち込みがあるの が理想的です。 波止や護岸からでもフカセは当然可能ですが、なんとなく気合が入らない ので、地磯やテトラを求めてさまよっています。 |
| 季節 | 春:のっこみ期は、がら藻が密集したような浅場を選びます。沖に深みの あるポイントであれば、早期から狙えます。とにかくチヌを集め、如何 にポイントに留まらせ、さらに浮かせるか、ですね。 ↓ のっこみ後に一服する時期がありますね。ただのっこみは場所によっ て若干時期にずれがありますので、過去のデータからタイミングを推測 して出掛けると良いかもしれません。 ただ、体力の回復を待つ産卵後のチヌを無理に釣るよりも、この時期は クロ(グレ)が出始める時期でもありますので、こちらを狙ったほうが良い かも知れませんね。 ↓ 夏:だんだん当年物や2年物の小形が活発に餌をあさり始め、また餌取りも 多くなります。フカセで型を出すのは難しいですね。なるべく足の速い餌 取りがいないポイントを選びます。 ↓ 秋:良型が出る可能性は高くはなるのですが、餌取りが全盛なのもこの 時期。もっとも腕の差が出る時期ですね。夏もそうですが、沖のポイン ト(深み)にピンポイントで仕掛け、撒き餌を入れる力があれば、この 時期でも型が狙えますが、なかなかねぇ..... ↓ 冬:晩秋から初冬にかけては、1年で一番チヌ釣りが面白い季節です。 餌取りも徐々に減ってきて、チヌの活性も高い状態です。 ただのっこみ期のように広範囲からチヌが寄ってくることはあまりない ので、チヌの棲家や通り道、また潮のよどみや反流点などを読み取り 積極的に攻めていく必要があります。 ↓ 厳寒期:水温が下がってくると、余り餌を追わなくなります。深場などの水 温の変化の少ないところでじっとしているようです。ただ、最近は暖冬 の影響でしょうか、あまり海水温が下がり切らないことが多く、深場を じっくり攻めると、通年チヌが釣れるようです。 実は僕、結構この釣れない時期の釣りが好きだったりして... 寒さに震えながら、わずかなあたりを待つ自分が、いいなぁ、なんて思 うのはおかしいでしょうか? |
| 釣り方 | まずポイントの潮上に1〜2投ほど撒き餌を投入します。このときはなるべ く撒き餌がバラけるように投入したいです。 仕掛けを撒き餌より若干潮下に投入します。 直ぐに道糸のたるみを回収し、仕掛けに張りを与えます。イメージとしては 浮きから針までが一直線になるように若干仕掛けを引き戻しながら、先に 投入した撒き餌の帯に刺し餌を併せます。 この操作をしつつ、もう一投撒き餌を浮きの潮上に入れます。 仕掛けの張りは重要ですが、あくまで撒き餌と刺し餌の一致が一番です。 張りに気を取られすぎて、撒き餌から刺し餌が外れないよう気を付けない といけません。これが難しかったら、張りは無理に作らないほうが良いでし ょう。 |
| 釣り方2 | 餌取りが多い場合 撒き餌を大量に磯際に投入し、餌取りを足止めする.....と、いいます が、現実問題としては、餌取りを足止めするほどオキアミを撒くと、私の財 布は直ぐにスッカラカンになってしまいます。 そこで、 餌取りの頭がすべて撒き餌に向くまで、撒き餌を一点に投入する。 仕掛けを潮下に投入する。 仕掛けの着水音を聞いて直ぐに餌取りが刺し餌のほうに来ようとするの で、ここで間髪入れずにもう一度元の撒き餌の投入点に撒き餌を入れる。 仕掛けを沈めながら、先に打った撒き餌に刺し餌を併せていく。 |
| 釣り方3 | それでもやっぱり餌取りが... 前述の方法で、さらに刺し餌が少し沈んだタイミングで、浮きに撒き餌をか ぶせて投入する。 これは、少しでも餌取りの意識を刺し餌から遠ざけるための苦肉の手段で して、決していつもいつもうまく行きません。 後は、 鯔の登場を待つ。 鯔が餌取りを排除してくれます。鯔の群れの真中に刺し餌を入れます。 チヌの活性があがるのを待つ。 ひたすら我慢して撒き餌をします。いつかチヌが餌取りを蹴散らしてくれ るのを待って。 あきらめて餌取りを釣る。 小アジだって、ベラだって、結構美味しいですから.... ・・・・・・・・・・・・・あ〜悔し....... |