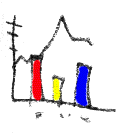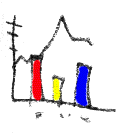
特集:嗚呼,我が受験人生
○はじめに
このページでは私の受験人生について語っていこうと思います。
以前は「公務員になる方法」というお題で,公務員試験に特化したページを作っていました。
しかし,私が公務員試験を受験したのは’97年の夏であり,もう四半世紀近くが経過しています。
公務員試験の勉強法等についてはいつの時代も変わらないと思いますが,さすがに当時の参考書の多くが今は存在しないと思われるため,私が使用した参考書など具体的な部分については割愛し,当時の経験等のみを記載したショートバージョンに改訂することとしました。
ただ減らすだけでは芸がないので,私の経験した中学受験,大学受験及び公務員試験について,サービス縮小を誹られない程度のボリュームを保ちながら書いていきたいと思います。
なお,従前の公務員試験ページと背景と文字の色を変えていないのは,私の受験経験のイメージカラーであるブラック&ブルーを強調したかったからです。
えらい長くなってしまいましたが,それでは本文をどうぞ。
※一部に過激な表現がありますが,当時の私の状況・心情をそのまま掲載しています。ご了承ください。 (苦手な方はブラウザバック推奨)
※今は「センター試験」は「共通テスト」に,「社会」は「地歴」となっているようですが,ご容赦ください。
※記述は全て私個人の印象及びネット等で調べた情報によるものです。間違っていても責任は取れませんので,必ず自分で調べてください。
中学受験編
大学受験編
公務員試験編
第一章 中学受験
私が中学受験をしようと考えたのは,恐らく小学校4年生の頃であったと思う。
私が住んでいた街にあった広島市内の某公立中学校が当時荒れに荒れており,恐らくここでは生きていかれないだろうと考えたのが発端である。
進学塾には,小学校5年生から通った。
何の気なしに入塾試験を受けてみたところ成績が非常に良かったらしく,是非入ってくれと誘いを受けたのである。
小さな教室であったので,そこでの成績は常にトップであり,広島県内全体でも50番以内には位置していた。
当時の広島の「男子御三家」と言えば国立の広島大学附属,私立の広島学院と修道だったが,この成績であればいわゆる「合格濃厚圏内」には入っていた。
よって,中学受験で成績に苦労した覚えは殆どない。
唯一の問題は,小6の夏に親父が岡山に転勤になって引越したことであった。
岡山では某大手の塾に通ったが,最上位クラスへの転入を,「うちは特別なことをやっていますから…」という理由で断られた。
上から2番目のクラスに入れられたが,塾内のテストで最上位クラスのトップの奴に勝利し,その所為か途中から最上位クラスに入った。
そこでは毎日鬼のような量の宿題が出され,泣きながらやったものである。
しかし私に言わせれば,あのようなやり方は無駄で愚かなものであったと思う。
あんなことをしなくても十分合格はできるし,むしろ勉強が嫌いになったり人格に影響が出たら元も子もない。
結局中学受験は広島の学校を受けた。
当時の岡山の国立・私立の中学は広島の上位校に実績の上で及ばなかったし,何より岡山に住むのはもう懲りていたからである。
広島大学附属と広島学院は自宅からの通学必須であったため,下宿の斡旋があって県外受験OKの修道のみを受け,めでたく受かった。
はっきり言うが,自慢話である。
しかし,難関大学への進学を欠片でも考えるならば,このくらいの能力は必要だと思っている。
なお,母校である修道についてのページを作成したので,よろしければご参考までに。
さて,私の話はここまでにして,ちょうど我が娘が中学受験を終えたところであるので,現状を見た雑感を書いていきたい。
<中学受験は必要か?>
正直言うと,「人による」としか言いようがない。
うちの長女の場合は「女子校に行きたい」という私から見ると理解不能な理由で中学受験をした。
このように,何らかのこだわりがあって「○○中学に行きたい!」という場合は文句なく受験をした方が良いだろう。
どちらかと言うと精神的に早熟で,大学進学から将来をぼんやりとでも考えている場合も中学受験向きかも知れない。
地域の公立中学が荒れているなどどうしても行きたくない事情がある場合も中学受験をした方が良いだろう。
要するに,中学受験を要する学校に行った方が幸せになれそうだ,と本人が思っている場合に中学受験を勧めたい。
間違っても親が「しなさい!」と押し付けるべきものではない。
特に広島の場合は特段中学受験をしなくても,上述したように高入の公立校にもまあまあの進学校があるので,中学受験を回避することで大学受験に極端に不利になるということはない。
ていうか,広島の学校であれば,それなり以上の進学校であればどこに行っても大差ない。
「できる子」「地頭のいい子」であれば,過程(中・高校)はどうあれ最終的には「あるべき場所」に行き着くことになるだろう。
間違えてはいけないのは,上述したことと重なるが,最難関校に入ったからと言って難関大学進学が約束される訳でもなければ,そうでないからと言って難関大学進学を諦めなければならない訳でもない。
正直広島という地方都市でのコップの中の争いであり,最難関校で努力をして上位をキープできる者はともかく,そうでなければ「6年間(あるいは3年間)何やってたの?」と思うような進学先になることは大いに有り得るし,最難関校以外からでも東大はじめ超難関大学に進学する例はいくらでもある。
大学進学に関して言えば,全ては入ってからの勝負になるということは補足しておきたい。
<中学受験有害論について>
ネット記事で見たのだが、「中学受験をして私立中学に入った子どもが公立中学生を『偏差値が低い奴ら』と言って侮辱した!このような歪んだ人間が育つから中学受験などやめてみんな公立中学から高校受験を目指すべきだ!」と論じている者がいた。
私から見れば大きなお世話であり、上述のとおり「したい者がすれば良い」のである。
たとえば私は小6の時に岡山に転校し、そこの学校(岡山で一番の文教地区と呼ばれる学区である)で苛烈ないじめを受け、こんな連中と一緒に持ち上がりで公立に行くなど死んでも御免、ということで受験勉強に勤しんで私立に行った(中学受験の勉強は以前からしていたが)。
上述の論を唱える者は、私のような者を目の前にしても同じことが言えるだろうか。甚だ無責任である。
荒れている公立中学校というものは存在する。
私が聞いたところによると、とある中学校においては、男女が授業をサボって公園にしけ込み、便所で猿のように性行為に勤しんでいるという。
このような環境に我が子(特に娘なら尚更である)を置きたいとは思わないだろう。
上述の論を唱える者は、我が子が公立中学に進んだ結果このようになったとしても文句を言ってはいけない。
そもそも、高偏差値の私立中に入った者が公立中の者を侮辱する背景はどうなのだろうか。
私のような目に遭って公立小学校(クラスメイトや教師など)に恨みを抱き、それが高じて上述のような暴言を吐いた可能性がある。
そうであれば、論われるべきは公立小・中学校で為される「公教育」についてではないか。
公立中学から公立高校に進むには「内申書」が重視され、この「内申書」は教師の好き嫌いで恣意的に作られる、と評判が悪い。
これを嫌って中高一貫の私立に進む子も少なからずいるのである。
なお、私の姪は公立中学から公立高校への進学を目指しているが、箔を付けるために生徒会活動をしているという。
このような状況が果たして正常と言えるだろうか。
さらに言えば、現在の公立小・中学校ではブラックな勤務環境により教師が疲弊しており、児童生徒に寄り添う余裕がない。
いじめなどの問題行動があったとしても、それに真摯に向き合う余裕がない。
まず公立小学校・中学校の教員を大胆に増やしてゆとりを作って環境を改善し、公教育を再生させることが必要であろう。
<塾について>
現状,少なくとも一般の公立小学校では中学受験に対応する授業をしていないので,受験をする場合は塾通いはほぼ必須だと言える。
現在であれば,附属・学院・清心レベルを目指すのであれば遅くとも小5(正確には小4の2月)から通うべきだろう。
それ以外であれば,小6(小5の2月)からでも何とかなると思う。ただし個人差があるので,絶対ではない。責任は負えないのでそのつもりで。
(公立一貫校は「適性検査」というやや特殊な形態での試験となることから特別な対策を要し、その分の時間はかかる。)
そうなると塾選びの話になるが,私の経験上,次の条件を満たしている塾を選ぶのが良いかと考えている。
1 「中学受験対策」をきちんと謳っている。
2 歴史が長い。
3 規模が大きい。(各地に教室を持っている。)
4 個々のレベルに応じたクラス分けがあり,一クラスの規模は小さい。
5 信頼できるレベルの模試を行っている。
6 家から近い。
1は当然と言えば当然であるが,塾の中には進学を主とするもののほか,学校の成績を上げることを目的とするものもあるので,きちんと確認すること。
2と3は信頼性の問題である。当然このようなところであれば,受験に関するノウハウをしっかりと持っていることが期待できる。
4はきめ細かいケアが出来るかどうか,という視点から重要である。極端に成績の違う子と同じ授業を受けさせられることは不幸である。
5については,やはり塾外のライバルも含めてその学校を志望する者たちの中で自分がどのくらいのところにいるのかを測るため必須と言える。
6はできれば,という点で挙げた。私は遠方にバスで通っていたが,結構辛かった。また,女の子であれば身の安全も心配になるだろう。
ここに本来入れなければならないこととして,先生が熱心であるかどうかということや,塾の雰囲気が自分に合うかということはある。
ただ,これは入ってみないと分からない部分があるので,「入る前」のチェックポイントからは除いた。
それなりの塾であれば問題はないと思うが,心配ならば入塾試験などの機会を通じてチェックしておくと良いだろう。
ただ,学校ではないのだから「嫌ならやめれば良い」という割り切りも必要である。
なお,通っている塾が合わないと感じたら(可能であれば)さっさと転塾するのが吉である。
うちの次女は9月終わりに塾(というか,通っている教室)に行くのを怖がって行けなくなった。
結局その時は塾と教室の所属は変えず,教材を受け取って授業は録画したものをもらい,家で親が勉強を見ることになった。
しかしこれはかなり現実的に難しいものであり,結果的には失敗だったと思う。
さっさと転塾するか,無理でも他の教室に所属を変えるべきだったと後悔している。
ちなみに上述の6条件は,必ずしも中学受験に限ったものではないと言える。
高校受験や大学受験,もしかしたら公務員試験にも当てはめることができるのではないだろうか。
<参考書・問題集について>
うちの娘二人について言うと,問題集の類は殆ど買っていない。
基本的には塾のテキストだけで十分であり,下手に分厚い問題集など買おうものなら消化不良を起こすのが目に見えている。
参考書も,期間が1年しかなかったこともあり,できるだけとっつきやすく,見てすぐ分かるものを選んで買い与えた。
ただ,幅広い知識をインプットする必要がある場合(特に理社)は「辞書代わり」として記載量の豊富な分厚い参考書を使うこともあった。
何を買ったかを挙げると長くなるし,数年経てば変わっていくものなので書かないが,ネットで比較的評価の高いものであればハズレはないだろう。
娘が何に苦労しているかを見極めて,それに対して手当てができるような本をその都度選んで買ったというのが実際のところである。
また,私が個人的に大切だと思うのは,模試や過去問である。
模試については,「とにかく間違えたところを何回もやりなさい」と娘には言っていた(実際やったかどうかは定かではない)。
過去問については,一通り知識習得が終わる6年生冬休みの段階から塾でもらって数年分はやったようである。
これについても,間違えたところを何度も復習して志望校の傾向を掴み,理解を深めることが望ましい。
なお,「どれくらいできたか」「合格点に達しているか」ということは考慮する必要はない。
どうしても気にはなるところだろうが,次女は5年分過去問をやって一度も合格点(推定)を下回ることがなかった某校が補欠だった。
過去は過去であり,状況は変わる。一喜一憂するべきではない。
あくまで過去問は教材の一つと割り切ってやるべきである。
前者はインプットであり,後者はアウトプットの話である。
娘たちの僅か1年間の受験生生活においては十分に出来たとは言い難いが,インプットはとっつきやすいもの,分かりやすいもの,見て分かるものを重視し,アウトプットはとにかく間違えたところ,苦手なところの反復学習を重視する,というのが私の考え方である。
なお,私は「考えても分からない問題は答えを見ながらやりなさい」と言っていた。
分からないからと言ってそこで止まっているのは時間の無駄であるし,答えを見て理解できればそれでOK,と考えたからである。
私のやり方が正しいかどうかは分からないが,一応合格通知をもらうことができたので,少なくとも大間違いではないだろうと思う。
<模試の判定について>
はっきり言っておくが,全くと言っていいほど気にする必要はない。
Dにはるか遠いE判定であれば別だが,そうでなければ合格を諦める必要はないし,逆にA判定だからと言って慢心は禁物である。
うちの娘はA判定しか取ったことのなかった学校が補欠だったし,私自身も大学受験の際、同様に確実と思っていた立命館大学に落ちている。
塾が行っている模試の中には受験校とレベルが合わなかったり母集団の人数やレベルに問題のあるものもある。
また,そうでなくても合否判定など受験校のさじ加減一つで変わるものなので,あくまで過去の実績に基づく判定を盲信するのは考え物である。
特に直近で定員を減らした学校や,その定員減の影響が及ぶ学校については少し厳しめに捉えた方が良いだろう。
<「魔の季節」を考える>
ネット記事によると、中学受験における「魔の季節」は6年の夏〜秋にかけてだそうである。
うちの娘二人についても、この時期に大きな試練があった。
二人ともこの季節に成績が伸び悩み、特に次女は自信をへし折られて塾に行けなくなった。
ただ、ネット上で言うところの意味と我が娘に関するところの意味は少々異なる。
前者について言えば、主に首都圏の中学受験に関するものである。
首都圏の子は遅くとも小4くらいから受験勉強に取り組んでおり、秋以降に新しくやることはほぼない。
このため、今後どんなに頑張っても飛躍的に成績を伸ばすことは考えにくく、最悪志望校の再考を余儀なくされる。
この点で子どもは現実を直視する必要があり、場合によってはメンタル不調に陥る危険性がある。
後者即ち我が娘について言えば、受験勉強は1年限定の「ゆる受験」である。
以前から受験勉強をしている子どもたちは、上述のように必要な内容の学習はほぼこの時期に終わる。
逆に我が娘のようにスタートが遅かった子は、理科社会を含めてまだまだやることが残っている。
このため、以前から受験勉強をしている子どもたちとそうでない我が娘たちの差が最も大きくなるのがこの期間である。
また、この辺りから模試の問題が入試を見据えてレベルが上がってくる。
このため、今までまずまずの点が取れていたのに、秋の模試では予想外に出来が悪かった、ということが多い。
よって、首都圏の子どもたちや以前から取り組んでいる子どもたちとは別の意味でメンタルケアが難しい。
この時期になると、モチベーションが大きく下がる子どもも出てくるだろう。
彼ら、彼女らの「やる気スイッチ」をどう押してやるのか、親としては思案のしどころである。
私はこれが下手糞だった(私がいくら言っても聞いてくれない)ので、奥さんに全て委ねてしまった。
大変申し訳なく思っている次第である。
<専願について>
2024年から、広島女学院において専願制度を導入した。
一部上位校以外は多くの学校で専願制度を導入しているが、この制度によるメリットとデメリットを挙げてみる。
[学校側]
メリット:生徒を確実に確保できる。実力上位の子が専願受験してくれれば、生徒の質向上も有り得る。
デメリット:合格者最低レベルは下がるため、下位層の学力レベルが下がる。いわゆる「偏差値ランク」が下がる。
[受験生側]
メリット:「ここに行きたい!」という意志があるのであれば、合格しやすくなる。
デメリット:併願の場合不利になる。専願者より実力上位であっても落ちる危険がある。
広島女学院について言えば、日能研のR4偏差値が4ポイント下がった。
ただ、家庭学習研究社(広島の老舗塾)によれば、同塾の会員のうち専願受験者11名がND清心を蹴って女学院に進学したという。
受験生としては、特段のこだわりがなければ、複数校を受験してより上位校に行きたいと願う者が多いだろう。
しかしそのつもりで併願受験した場合、思わぬところから不合格を突き付けられるリスクがある。
確かな受験戦略が要求されるが、所詮合否は各校のさじ加減であり、専願でどれだけ下駄を履かせるかはブラックボックスである。
「本人の意志がある程度確かならば専願」というやり方に傾かざるを得ないと思うし、本人の意志が重要な要素となるだろう。
<繰り上がり合格について>
次女がこのたび、「補欠→繰り上がり合格」という稀有な(あまりしたくない)経験をしたので、一応綴っておく。
まず、「補欠合格」がなぜあるかというと、「正規合格者だけでは定員を埋められない可能性があるから」である。
トップオブトップの学校を除けば、「上位校に合格者を奪われる」という宿命から逃れることはできない。
このため、各校はある程度逃げられる数を見積り、その数を上乗せして合格者を出す。
しかし、それでも定員を充足できそうにない場合に、一定程度「補欠」を確保しておき、彼らに「繰り上がり合格」を出す。
当然ながら、上位校ほど補欠は少ないし補欠から繰り上がる可能性も少ない。
広島で言えば広大附属は補欠が少なく、繰り上がりはさらに少ない。
逆に修道などは志願者が多いが上位校に行く子も多いため、合格者も多く出すし補欠もかなり確保している。
無論、補欠から繰り上がるのは相当惜しいところで落ちた子だけであることは間違いない。
私は次女が補欠になったことを知った時、「何かの間違いじゃねえのか!?」と思ったくらいである。
そのくらいのレベル差でなければ繰り上がりを期待してはいけないと思う。
よく疑問として挙がるのが、「どれだけ待てばいいのですか?」ということである。
早ければ合格発表から4〜5日後であろう。(うちもそうだったし、受験掲示板でもそのくらいと記載されていた。)
ただ、上位校(又は競合校)の発表・上位校(又は競合校)の入学手続きに加え、「手続きをした後に他校から繰り上がり合格をもらった」という子がぎりぎりになって辞退することもあるため、「上位校(又は競合校)の制服の採寸」のタイミングで繰り上がることもある。
繰り上がり合格については各校が「○○日までです」又は「○○日に締め切りました」とアナウンスするはずなので、それまでは可能性はある。
<いきなり難化問題>
広島県内で言うと、崇徳が共学化を機にいきなり難化したという評判である。
また、広島なぎさも2025年入試において、前年と比べて合格者数を100名近く減らしている(補欠からの繰り上がりが何人かは知らないが)。
少子化ということもあり、御三家未満の中堅私学については定員充足を選ぶか、あるいは人数を削ってでも質を保つかは大きな問題である。
上記2校は後者、しかも従前よりも厳しい選考をすることでさらに質を上げることを目論んでいるということだろう。
こういうことがあるので、たとえば過去問で「合格最低点」をクリアしていても安心してはいけない。
さらに言うと、広大附属福山は2027年から中高一貫の「中等教育学校」となるようである。
このようなことがいきなり決まったりもするので、常に情報のアンテナを張っていないといけない。
<各科目別の留意点>
※あくまで私見です。
[国語]
娘二人は両方とも公文をやっていたので、ある程度の素養はあった。
ただ、上位校の物語文や論説文については、短時間で長文を読み解く力を必要とする。
これは一朝一夕に鍛えられるものではないため、多くの問題を読みこなすしかないだろう。
ネット記事に「問題文に丸や矢印を書き込み、どこの文章がどこの伏線になっているか分かりやすくする」というやり方が載っていた。
これは大学受験の記事であり、中学受験に応用できるかは分からないが、突破口になる可能性はあるだろう。
あとは漢字、ことわざや四字熟語などの暗記物も重要である。中学入試のみならず、社会に出てから常識を問われるので。
[算数]
最もキーになる科目と言って良いだろう。
上述したように、国語の能力を伸ばすことは簡単ではないが、算数は解法とその使いどころを覚え込めば成績がぐんと伸びる。
とはいえ、それを覚えるためには相当量の問題演習が必要となるだろう。
まずは解法(つるかめ算や旅人算など)を覚え、それを使った基本問題をやって使い方を覚え、あとは過去問などの実戦用の問題を解いて「こういう問題の時は○○算を使うんだな」というパターンを覚えていく。
やればやっただけ点数になるので、根気よく進めていくことが必要であると言える。
[理科・社会]
娘二人は受験勉強を1年しかやっていないので、理科と社会の進度は死活問題であった。
これらは国語や算数と比べると配点が低いあるいはそもそも試験科目にない学校もあるので、どうしても後回しになりやすい。
まず第一に重要なのは、模試や過去問において「知らない」「見たことがない」分野をなくすことである。
参考書(自由自在など)を買っておいて、そのような分野に付箋を貼るなどして意識的に覚え込むのも一つの方法である。
基本は暗記なので、できるだけ知識の穴がないようにしなければならない。
理科は計算問題もあるので、算数同様に実戦的な問題演習も必要だろう。
中学受験の闇へ(閲覧注意)
第二章 大学受験
最初に申し上げるが,私の大学受験は結果的には失敗であった。
第一志望の大学であった京都大学法学部に入れなかったからである。
敗因分析をかねて,大学受験成功のために必要なことを(反面教師として)綴っていきたい。
<塾について>
まず重要なのは,塾選びである。
私が受験した時は河合塾と代々木ゼミナールしか選択肢がなかったため,高2から河合塾に入った。
しかし,少なくとも私にとっては河合塾は肌に合わず,志望校合格の役には立たなかった。
理由としては、
1 規模が大きすぎる。
いわゆる「マスプロ授業」である。
特にレベル不問の科目別授業(「古典」など)に多いのだが、酷い時は100人以上から入るような大教室に詰め込まれての一方的な座学。
また、大規模な塾には大体「自習室」があるが、上述の「大教室に100人以上」状態であれば、まずうるさくて勉強できない。
周りの友達と喋りながら勉強(?)する奴らはそもそも自習室に来るべきではないのだが、現実はそんなものである。
2 レベルが合わない授業を受講。
上述の「レベル不問の科目別授業」を受けた場合、ある人にとっては「ついていけない」になるし、またある人には「分かっとるわ!」になる。
いずれにしても金をどぶに捨てる結果となるのは同じである。
3 「東大・京大コース」を受講。
最もレベルの高い受験生が受講するコースは「東大・京大コース」であった。
これは読んで字のごとく、東大と京大の受験対策を行うものであったが、東大と京大では問題の傾向が違う。
本来ならば東大なら東大、京大なら京大の対策に特化する方が効率的であったと言える。
今河合塾のホームページを見ると、上述の欠点はある程度改善されたように見える。(自習室は知らないが)
レベル別、学校別対策講座(東大英語、京大英語など)の中から取捨選択し、必要な講座を受講する仕組みとなっている。
このように、今の自分に必要なレベルの必要な授業だけを受けるようにしないと、金と時間をどぶに捨てることになる。
塾に通うに当たってはしっかりと吟味しておきたい。
今広島には駿台,東進,四谷学院といった全国の有名進学塾が進出しているので,受験生にとっては幸せな環境だと思う。
河合や代ゼミをディスる訳ではないが,やはり東京や大阪などの大都市圏の受験生と張り合うためには,塾の選択肢は多い方がいいに決まっている。
自分のニーズに合う塾に出逢えれば、志望校合格への道は広がるに違いない。
ただ、最大の成果を得ようと思えば、相当程度の課金を求められる可能性がある。評判だけでなく、コスパも考慮しなければならないだろう。
<基礎学力について>
上記の文章を読むと、私が大学受験に失敗したのは塾の所為のように見えるだろうが、実際はそうではない。
現役時の私は京大合格に必要な学力が決定的に不足していたと思う。
私の時だって河合塾に通って合格する奴はちゃんと合格していたし、塾に行かなくても自分で勉強する手段はいくらでもあった。
そもそも、後述するように現役時の私は併願した私大にも落ちている。これは言い訳ができない。
後述するが、特に現役時に足を引っ張ったのは数学であった。
何せ学校の実力テストで、中2の時点で代数で21点、幾何で29点を取っていたくらいである。
本来ならこの時点で相当危機感を持って取り組むべきであった。
多分勉強はしていたと思うのだが、記憶にないところを見るとそのままだったのであろう。
このレベルであれば、少なくともこの時点のこの分野においては「学校の勉強についていけていない」ということである。
これが積もり積もって高3になって基礎学力不足に繋がっていったのである。
中学の時点から、このような兆候が見えた時点で危機感を持って苦手を潰しておくことが、将来苦しまないための最善の対策である。
また、受験生時代の私は、布団に寝転がってテレビをつけっぱなしにして深夜勉強をしていた。
これでは知識が頭に入る訳がない。
この辺りをもってしても、現役時の私は受験勉強に対する取り組みが甘かった訳であり、歴戦の猛者が集う京大入試に敗れたのは必然だったと言える。
<各科目について>
※あくまでも私見です。
[国語]
得点源であった。
校内偏差値で言えば、他科目が53とか55とかであった中で国語だけ73であり、間違いなく天才であると自称して憚らないレベルであった。
現代文は、中学入試の項で少し触れたテクニカルなこと以外はほぼ才能であり、少々やったところで飛躍的に伸びるものではないと思っている。
古文と漢文についてはある程度努力が物を言う。国語のセンスは確かに要るのだが、努力次第で差を埋めることは可能である。
対策としては、とにかく文章を読みまくることだろうか。志望校の過去問などを読み、「好きそう」な傾向を掴むことは有効と思う。
※京大では私の頃は「近代文語文」が出題されていた。今は一橋で出題されるそうなので、志望者は要対策だろう。難しいとは思わなかったが。
[英語]
苦手ではなかったが、得意でもなかった。
ただ、基礎学力のなさが節目節目で悪い方向に働き、併願私大に落ちたりセンター試験に失敗して京大を諦めることに直結した。
私が自身の失敗から重要と痛感したのは、文法と語彙力である。
文法はセンター試験や私大入試では非常に重要なものであるし、語彙力がなければ長文問題を読み切ることが難しくなる。
これらをすっ飛ばして背伸びをして志望校対策をしたとしても、大きな効果は得られないだろう。
英語の点が伸びないのであれば、この2点を徹底的にやり直してから挑んだ方が良い。
京大二次は英文和訳と和文英訳の二本立てであり、いわゆる「教科書英語」ではないこなれた訳を求められる。
たとえば、ことわざや慣用句を英訳することを求められたりもするので、普段から英語で考える癖を付けた方が良いかも知れない。
[数学]
現役時に最も足を引っ張られた科目であった。
上述したように中学時代から苦手であり、その意識を高3まで引っ張ったのが最大の敗因である。
個人的に言うと、まず「数学嫌だなあ、やりたくないなあ」というところからまず変える必要があった。
効果があったと言えるのは、浪人時に取り組んだ「大学への数学」だろうか。
確か今もあるので書いておくと、若干マニア向けと言えるレベルで、特に理系や東大・京大など難関校受験者が愛読する雑誌である。
これの「学力コンテスト」に参加し、大抵は玉砕していたが,たまには良い点をもらうこともあり、これは大きな自信になった。
何より、苦痛でしょうがなかった数学が「ちょっと面白いんじゃね?」くらいの認識に変わったのである。
英語の項とは矛盾するが、こういった難問に取り組む中で、基礎にもう一回目を通して習得し直すということも出来たように思う。
現役時と浪人時で最もレベルが上がったのは数学であると個人的には思う。まあそのレベルアップが役に立ったかはまた別の話だが。
[社会]
京大(文系)は私の受験当時は、センター試験で1科目、二次試験で別の1科目を選択して受ける必要があった。
私はセンターでは世界史を、二次試験では日本史を選択した。
私は日本のことは誰より良く知っている自負があったが、世界のことには無知だったので、日本史は得意だったが世界史は精々普通だった。
一番役に立ったと思うのは、小学館の「まんが日本の歴史」であった。一部のマニアックな問題(以前の早慶で出ていたような問題)は別として、そうでなければ大学入試はこの本を読んで覚えれば十分である。
ただ、京大二次は記述式であり、「漢字で書きなさい」と指定される場合があるため、「書き問題」の練習も怠らずやっておくこと。(詳細は後述)
[理科]
私は地学選択であった。
文系で、なおかつ理系科目はできるだけ避けて通りたい人には地学はお勧めである。
何せ何もしなくてもセンター6〜7割は確実に取れる、と言われた科目である。
無論本当に何もしなかったら酷い目に遭うと思うが、ほぼ暗記科目であり、コスパ・タイパには優れていることは間違いない。
<(不)合格体験記>
上記の状況を踏まえ、私の経験を書いておく。
[現役時]センター試験:725/800点、前期:京大法×、後期:京大法×、併願私大:立命館大法×
見れば分かるが、惨敗である。
センター試験の時は何故か割と精神に余裕があり、「さあて、どんな問題が私を楽しませてくれるのかな?」くらいの気分であった。
それが功を奏し、またこの年は易化していたこともあって9割以上の高得点をゲットし、有頂天であった。
※特に国語は198点であったが、マイナス2点は漢字(「彼我」という単語を知らなかった)であった。これは今でも忘れない。
で、前期も後期も意気揚々と京大にぶっ込んだ。※当時は京大も後期試験があった。
後期は安全策を取ってやや難易度が下の大学(阪大や神戸大など)に出願する向きも多かったのだが、私の場合は後期の方が数学がない分有利だと思っていたので、迷うことなく京大に出願したものである。
ただ、そんな私の鼻っ柱を叩き折る出来事があった。
併願の立命館大に落ちたのである。
立命館は社会か数学を選択でき、「京大受験に向けた練習である」と嘯いて数学で受けたのだが、見事に落ちた。
数学の実力がそこまでダメダメだったということなのだろうが、この時はあまり危機感を持たなかった。
そして京大も実力通り落ちにけり、ということになったのである。
国語はそんなにできない印象はなかったが、恐らくあの集団の中に入れば凡庸なレベルだったのだろう。
英語や数学はお話にならなかったに違いない。
日本史では忘れられない問題がある。
記述問題で北海道の戦国大名の名を問われる問題があり、「蠣崎氏」であることは知っていたが、「蠣崎氏」の「蠣」の字が書けなかったのである。
問題文に「漢字で書きなさい」と書いてあったので,ひらがなでは0点である。
後述するが、私はかなり惜しいところで落ちたっぽいので「まさかこの0.5点(配点)で落ちたのでは…」と今でも悔恨の念が消えない。
後年私の地元広島で,名物の牡蠣に親しんでもらうために「牡蠣」の漢字ばかり書かせる漢字ドリル「牡蠣とり帳」なるものが誕生したが、私の時代にこれがあったならば私の人生は変わっていた可能性がある。
後期は元々相当高レベルでの争いであり、どのように採点されたのかは分からないが、逆転は望むべくもなかった。
最も残念だったのは、体調を崩したことである。
鼻水がズルズルの状態で受けたので、元々ない実力の、さらに数割減しか発揮できなかった。
一応学校の勉強と塾、さらにはZ会もやっていたので,全く通用しないというレベルではないと思っていたし、センター試験も良かったので何とかなると思っていたが、天下の京大は甘くはなかった。
こうして、めでたく全敗で浪人が決まったのである。
[浪人時]センター試験:651/800点、前期:神戸大法○、併願私大:早大法○、中央大法×、同志社大法×、立命館大法○、関西大法○
センター試験での失敗が全てを決めたと言って良い。
上述したように、浪人してから数学を割と真面目にやったこともあり、実力がついている自負はあった。
ただ、その自信とは裏腹に、「二浪はできない」という思いがあり、「センターは失敗できない」という変なプレッシャーが掛かったように思う。
大体こういう時は悪い方に流れるものであり、英語の手応えがなかったことから心に乱れが生じ、さらに数学もボロボロに落として泥沼に嵌り、前年比−74点という結構な記録を叩きだして惨敗した。
この時点で京大を諦めた私は、当時は大きな差がなかった(←強調)阪大と神戸大とどちらに出願するかに考えを切り替えた。
神戸大に出願した理由は、次のとおりである。
・傾斜配点上、センター試験で惨敗した数学のダメージが比較的軽い。
・神戸大は社会科学系を看板とする大学であり、実力的に阪大と遜色ない。
・阪大は体育でプールの授業がある(※)。
※私は中学時代に臨海学校で死ぬ思いをしたことがあり、生命の危機を感じたからである。なお、今はないらしい。
現役時は1校しか受けなかった私立も,この時はたくさん受けた。
なお,慶応と関西学院は受験していない。私の家の近所に結構な金持ちが住んでいて慶応に進学したが,周りと生活レベルが違い過ぎて孤独になり,毎日「みじめだ」と泣いていたという話を聞いたため,学力より前にまず生活レベルでついていけないだろうと考えたからである。
まず中央は普通に落ちた。理由は分からない。普通に受けて普通に落ちた。
同志社も落ちた。これは理由が分かっている。英語で異常な分量の長文問題が出て,圧倒されて心を折られたからである。
同志社はその校風からか,英語の実力を重視する傾向があるように思う。本気で目指す人は肝に銘じておくべきであろう。
他の3校はめでたく合格を手にすることができた。
前年「京大の前哨戦である」と嘯いて見事に落ちた立命館は、今回はなりふり構わず日本史で勝負してリベンジした。
関西は特に国語が冴えた。多分国語は満点だったと思っている。
最も驚いたのは早稲田である。ご存じの方も多いと思うが,ここの特に日本史は非常にマニアックで難易度が高い。これはさすがに太刀打ちできず,多分ダメだろうと思っていたら,受かっていた。
東大に受かった人でも,「早稲田に受かった時は東大に受かった時よりうれしかった」と言うくらいで,これは確かに大きかった。
日本史の難問はみんなできず,国語と英語でそれなりに取れたのが勝因だったのだろうか。
で,神戸大である。
はっきり言って京大に向けて勉強してきた身にとっては歯ごたえがなくて残念だった。
特に数学は易しく感じられ,あの勉強は何だったのかと哀しくなってしまった。
ここに関して言えば,合格に向けた特殊な対策は必要なく,基礎学力を固めておくことが何より大切だということを助言しておきたい。
(筆者注:ただし,近年は英語で比較的ボリュームのある問題が出題されるとのことなので,ここは注意した方が良いかも知れない。)
結果は目論見通りの合格。私の撤退戦略(予備校の京大クラスの友人からはブーイングの嵐だったが)は一応功を奏したと言える。
最終的に神戸と早稲田で悩んだ挙句,神戸大に進学することに決めた。
悩んだのは私だけのようで,高校の担任の先生など幾人かに相談したが全員が「神戸に行け」と言った。
元々国立志望であったし,東京の私大に進学したら金がかかり,親に負担をかけるということも要因の一つであった。
ちなみに高校の担任は最後まで「お前は京大に行かないといけなかったのになあ…」ととても残念そうに仰っていた。
現役時に京大に落ちた時,浪人する旨の報告に行ったところ,「あと何点で落ちたか知りたいか?」と言われた。
※高校にはその旨のデータが届くらしい。
その様子から察したので,丁重にお断り申し上げた。
こうして、私の受験生生活は幕を閉じたのである。
なお,神戸大学についてのページを作成したので,よろしければご参考までに。
<浪人について>
先日、私の甥が大学受験をした。
第一志望の超難関国立大学に前期で不合格となり、後期で準難関レベルの某大学に受かった。
私から見れば「彼ほどの実力者が某大学で良いのか」と思ったし、親(私の弟)も浪人を勧めたらしいが、拒否して進学するという。
言うまでもないが、浪人するしないは本人の自由である。
浪人すれば余程なまけない限り実力は上がるが、それが第一志望合格に直結するとは限らないのは私の例を見ても分かることであるし、何より人生のうちで貴重な一年間を受験勉強という、あまり生産的ではない活動に集中しなければならない。
両親に(程度の差はあるが)金銭的な負担をかけることを心苦しく思う向きもあろう。
私の頃は「一浪当然、二浪必然…」と言われていたくらい浪人が多かった。
第二次ベビーブームの真っ只中であり、ライバルの多い時代であったことも含め、浪人することに対する心理的ハードルも低かった。
しかし、今は東大でも合格者のうち浪人は2割程度であり、浪人すること自体が珍しい、までは言わないがメジャールートではなくなっている。
ただ、次に該当する場合は浪人するべきだと思う(とはいえ、精々一浪までだと思うが)。
1 時間的制約で十分に受験勉強が出来なかった。
2 受験戦略に失敗した。
3 どうしても第一志望に行きたい。
1について言えば、多くの私立中高一貫校では大学入試を見据えて先取り学習を行うなどのフォローをしているが、それ以外の学校(名門の国立でも例外ではない)ではそういったものがなく、また学校行事や部活をみっちりやる場合もあるため、本格的な受験勉強が出来たのは高3の夏からの約半年だけでした、ということもあるという。
2について言えば、たとえば東大を受験する場合、早慶は押さえておくのが一般的であり、早慶に受かれば後期は受けない者が多数派であるらしい。
早慶を押さえていなかった場合、後期だと横国辺りに出願することになるだろうが、仮に合格しても「満足できる結果」とは言い難い。
これは受験戦略の失敗であり、後に悔いを残す。現にこのような結果になった場合、多くが「受かっても行かない」又は「仮面浪人」を選ぶ。
なお、3については言うまでもないことだと思うので省略する。
ただ、いずれにせよ本人がしっかりと自分の頭で考えて決めることが大事なのは言うまでもない。
その結果がどう転んだとしても、自分で決めたことならば納得出来るだろう。いや、してもらわなければならない。
<おまけ:実際受けに行く方々へ>
最後に一つだけ申し上げておきたいのは、「下見はしよう」ということである。
私は京大受験の下見に行った時、出町柳駅から方向を間違えて鞍馬へ行きそうになった。
また、早稲田の下見に行った時に間違って埼京線に乗ってしまい、池袋まで強制連行された。
いずれも下見だったから良かったが、本番でやらかしていたらと思うと背筋が寒くなる。
ここまで豪快にやらかす人は極少数派だと思うが、当日会場を間違えるとか道に迷うなどは決して珍しいことではない。
余裕を持って受験に臨むためにも、正しい会場までの道のりを前日までに頭に叩き込んでおくことをお勧めする。
裏コーナーへ(閲覧注意)
第三章 公務員試験
私が公務員試験の勉強を始めたのは,大学3年の10月のことだった。
元々性格的に一般企業は無理,と思っていた私は,それなら勉強さえすればなれる公務員にでもなろうか,と単純に考え,勉強を始めた。
今となれば,こんなことを考える時点で企業だの公務員だのに関係なくそもそも勤め人に向いてなかったんじゃないのか,という気がしないでもないのだが。
さてさて,勉強,と一言で言っても,何から手をつけたらいいのか分からないわ分からないわ,という人は多いだろう。
私の場合は,まず予備校に通って,それまで知識ゼロだった経済原論(私は法学部だったので),数的処理(パズルみたいな奴),行政法(大学の授業が糞の役にも立たなかった)の3教科を習った。
この3つの他に,民法と憲法の計5科目が,配点の大きい重要科目と言えるだろう。まずはここからである。
ただ,3年秋の時点では予備校に通うだけで,本気で受験体勢にあった訳ではなかった。
本当に本腰を入れたのは,大学の後期試験が終わった翌年の1,2月くらいからだった。
この時にやったのは,とにかく知識を頭に詰め込むことで,そのために実務教育出版の通信教育を申し込んでそのテキストにアンダーラインを鬼のように引きまくって消化不良を起こしながらひたすら詰め込み教育。
その後春からは,専門試験(法律,経済…)は問題を解きまくり,教養試験(高校の勉強の延長みたいなもの)は予備校(LEC)の講座を取り,高校時代得意だった科目はなるたけその時の水準に戻るように,苦手だった,もしくは選択していなかった科目は超基本的な問題だけは出来るようにしていた。
こういう科目は捨てる人もいるかもしれないが,私は簡単な問題だけでも出来るようにしておいた方がよいと思うぞ。
私は本腰を入れ始めたころから試験直前の6月ごろまでずっと予備校の自習室に通って勉強していた。
と,こう書くといかにも模範的真面目な受験生に見えるかもしれないが,実は全くそうでなく,単に当時好きだった女の子がそこの予備校に行っていたから,という至極不純な動機が隠されていたのであった。
いいんだよ,何にしても勉強する原動力があるってのは。長い受験生活,それくらいの楽しみがないともちませんよ。
ただ,深入りはしないこと。特に男性。受験生同志で恋に落ちると,必ず男が落ちて女が受かって,新しい世界に飛び立った彼女の方が向こうで新しい恋人を作ってあえなく破局,というのが古典的パターンですからね。
変な話になってしまった。閑話休題。
春先からはひたすら問題集を解く。分からない問題はまだ多いかも知れないが,それでもいい。問題をやりながら覚えるのだ。
模試にひたすら土日を費やしたのもこの頃。LEC,実務教育出版などいろいろあるが,金と時間が許す限り受けてみよう。出来は二の次で構わない。試験の形式に慣れ,一問でも多くの問題に触れることこそが重要なのである。
そして,5,6月になるといよいよ大詰め。ここまで来たら,あとはひたすら過去問を解く。公務員試験はどうせ出る問題のパターンは決まっているので,過去問を解くのは非常に大事なのだ。ひどい時は,全く同じ問題が出ることもある。(私の時はあった。)
とまあ,アウトラインはこんな感じでやっていた。で,心構えを一言で言うなれば,
「公務員試験の勝敗を決するのは,ただ勉強量のみ。」
とにかく,どれだけやったか。それで決まると言って良い。とにかく範囲は無限にあるのだから,やればやっただけ合格に近づく。当たり前の話である。勉強すれば私のような奴でも受かるし,しなければたとえ東大生でも落ちるだろう。
さて,ここからは実践編と称し,各試験についての気付き等を書いていきたい。
私が実際に受けた職種及び結果は次のとおり。
○国家一種(現・国家公務員総合職):一次落ち
○国家二種(現・国家公務員一般職):最終合格
○地方上級:最終合格
○裁判所事務官一種(現・裁判所事務官総合職):一次合格,二次落ち
○裁判所事務官二種(現・裁判所事務官一般職):同上
国家一種については,ほぼ記念受験であった。受かる気もなかったし,何も言うべきことはない。
主なターゲットは国家二種と地方上級であった。これに関しては,現存するもので言えば実務教育出版の「受験ジャーナル」という雑誌を購読していた。
必要な情報の取得に役立つし,誌上模試も載っている。公務員試験受験生は恐らく皆読んでいることだろうが。
また,上述したように実務教育出版で通信講座もやっていたのでそれも利用した。
あとは公務員試験予備校としてLECに通っていた。司法試験などが有名だが,公務員試験についても模試を行っており,重宝した。
参考書については最近のものは分からないが,これらの有名どころが出している出版物であれば信頼できると言えるだろう。
で,各職種ごとの印象を少々。
○国家公務員総合職(当時の国家一種)
上述したように,受かる気がなかったのでノーコメント。
○裁判所事務官総合職(当時の裁判所事務官一種)
法学部学生御用達(?)。一次は他の試験(国家一種,二種)用の勉強+訴訟法,という形で勉強した。
私は民事訴訟法専攻だったため,訴訟法は民訴を選んだが,勉強法が難しい。
というのもこの職種用の参考書・問題集が絶滅危惧種レベル。特に訴訟法は困りもの。
民訴については,私は司法書士試験用のものを使った(問題に少々癖があり全く同じではないが)。
刑事訴訟法は司法書士試験の科目にないためさらに困る。司法試験用でも使わないといけないだろうか。
最も良い問題集は過去問。少ないながら過去問の載った問題集はあったはずなので,是非手に入れて対策に役立てたい。
そして首尾よく一次に合格しても,二次倍率はまだ5〜7倍程度あり,全く楽観はできない。司法試験組もおり,レベルも高い。
私が受験した当時,広島会場での一種一次合格者は2名のみ。最終合格者はゼロであった。
二次試験を私と共に受験した人が東大出身のお姉さんで,一緒に食事をして東大の面白い話を聞いたのは良い思い出である。
○地方上級・国家公務員一般職(当時の国家二種)
この二つは難易度がほぼ同じなので並行して受験する人も多いだろう。
地方上級は時に国家総合職並みの難易度の問題があったりしたが,そんな問題はどうせ誰もできないので気にする必要はない。
国家一般職は科目数が地方上級より多いのが特徴であった。ただ,実際には何問か捨てることができるので自分のできる問題に集中することが大切。
問題が難しいと感じる場合もあるが,難易度に応じてボーダーは下がるので焦らず自信を持って受ければ大丈夫,と言える。
両者とも一次試験については,上述のオーソドックスな勉強で十分対応できると言える。
二次小論文については,恐らくみんなの知識レベルは似たりよったりなので,あまり知識偏重にならず,自分の考えや決意を交えつつ,簡潔明瞭,論理的に書くのが吉。あと,字は丁寧に。備えとしては,行政や(地方上級であれば)地方自治に関する課題及びその解決策への提言,といった題材を扱った本をいくらか読んでおくと良いだろう。
また,地方上級であれば,地方紙などを読んで受験する地域のことを知っておくと役立つかも知れない。
集団討論は,あまり突出して過激なことを言うと却って逆効果になるので,自分の意見はきっちり主張しつつも,あくまでフレンドリーにやることを勧めたい。受かったら同期の桜になるので,「ここで友達を作っていこう」くらい思っていたほうが良いかも知れない。
○裁判所事務官一般職(当時の裁判所事務官二種)
二次で落ちたので(原因が分からない)何も言えないが…
一次に関しては,上述の地方上級・国家一般職レベルの勉強に加えていくつかの模試や過去問をやれば十分と思われる。
二次は論文で,裁判に関する教養と憲法について問われるため,それなりの学習と対策は必要。
あとは面接に備え,どんな仕事をするのかは事前予習しておこう。あとは変なことを言わなければ…大丈夫じゃないかな(苦笑)
なお,公務員に関する初歩的な疑問にお答えするコーナーを作っているので,もしお役に立てば御覧いただきたい。
------------------------------------------------------------------
とりあえずこんなところである。
以上は私が受験した時の話であり,今現在において受験の制度,受験科目,配点等変わっているところがあるかも知れない。
あくまでこれは昔の話として,参考程度に頭の隅にでもとどめていただければ幸いである。
そして今度はこれを読んでいるあなたが,私より役に立つ受験情報を後世に残していただければ有難い。
最後になったが,全ての受験生の皆様方のご健闘とご武運,ご成功を心よりお祈り申し上げる。